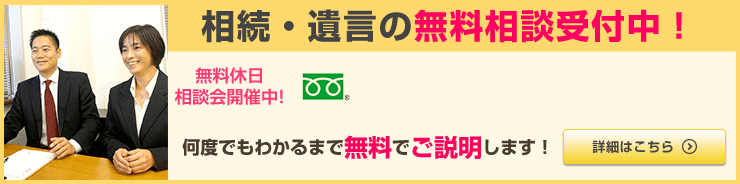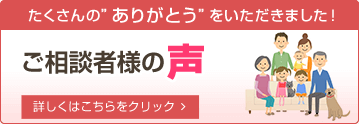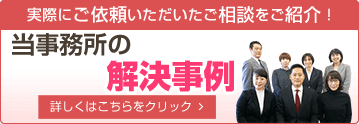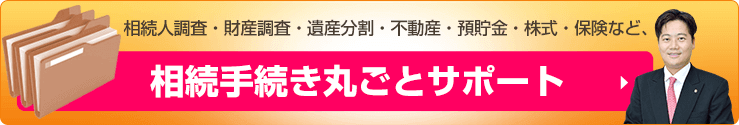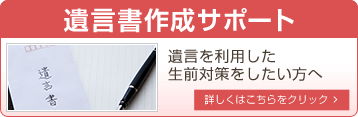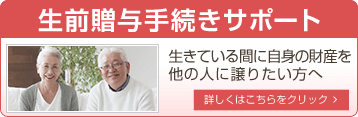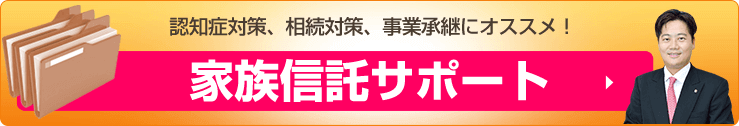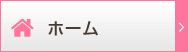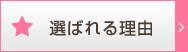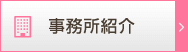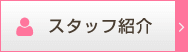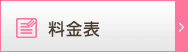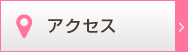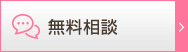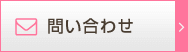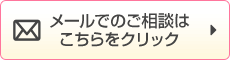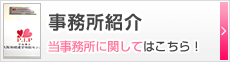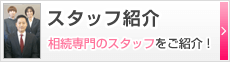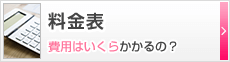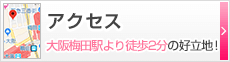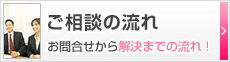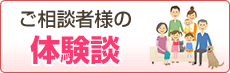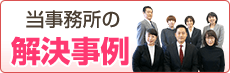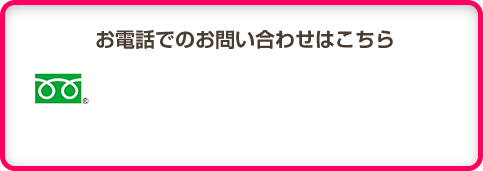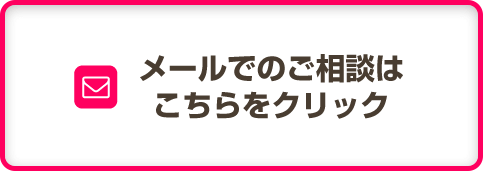預貯金と不動産の相続手続き~遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは?~
被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。
このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると、預金の払戻しが凍結されます。もしも、預貯金の保全が心配な場合、銀行に被相続人の死亡を伝えておくと良いでしょう。
凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
各金融機関毎の手続き内容に関しては、下記をご参照ください。
>>北おおさか信用金庫(きたしん)の預金の相続手続きについて
>>大阪シティ信用金庫(シティ信金)の預金の相続手続きについて
具体的な手続きは以下の通りです。遺産分割前の場合と、遺産分割協議書の締結後の場合についてそれぞれ解説いたします。
1.遺産分割の前に払戻しする場合
2019年7月1日に、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が施行されました。
通常、口座名義人が亡くなり、相続預金が遺産分割の対象となる場合には、遺産分割が終了するまでの間、相続人単独では相続預金の払戻しを受けられないことがあります。
そのため、遺産分割前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどでお金が必要になった際に、相続預金の払戻しが受けられる制度が設けられました。
必要書類
遺産分割前に相続預金の払戻しを受ける場合、金融機関に以下の書類を提出します。
①金融機関所定の払い戻し請求書 |
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。
現実的には、四十九日や法要などの費用で困った場合に、こうした手続きを進める形になりますが、基本的には遺産分割協議を行う前に、預貯金だけ払い戻すという事は、相続を複雑にしてしまうほか、遺産相続のトラブルにもつながるので、あまりお勧めは出来ません。
お困りごとがありましたら、まずはお気軽に相続の専門家にご相談ください。
2.遺産分割協議書の締結後に払戻しする場合
遺産分割協議書の締結後に払戻しする場合、以下の書類を金融機関に提出します。
①金融機関所定の払い戻し請求書 |
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。
現実的には、相続人全員で分割方法に合意が取れたうえで、預貯金の払戻しをするこの方法が、もっとも円滑な流れになると思います。相続の手続きを適当にしてしまうと、親族間の交流が無くなるほか、へたすると裁判にまで発展してしまいかねません。
また、裁判にしないまでも合意が取れないので、相続財産が一切、承継する事が出来ないという事態にもつながってしまいます。
正しい手続きを踏むことを第一にご検討下さい。
また、遺産分割協議書の締結語に払戻しをする場合でも、調停や審判に基づく場合と、遺言書に基づく場合で必要書類等が異なります。
調停・審判に、基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
①家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます) |
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。
遺言書に、基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
①遺言書(コピーでも可) |
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。
不動産(土地・建物)の相続手続きにも遺産分割協議書が必要になることがあります。
遺産分割等の相続手続きに関してお悩みの方はお気軽にご相談くださいませ。
無料相談実施中!

大阪相続遺言相談センターでは、相続・遺言等に関する質問に関しては、ご相談者様のことを第一に考え、初回の相談はすべて無料でお引き受けしています。どうぞお気軽にお電話ください。
お電話は、土曜・日曜も含め、毎日朝9時から夜9時まで受け付けています。また、事務所でのご相談も朝9時~夜9時まで受け付けています。ご希望の時間にお電話、ご相談いただけたらと思います。
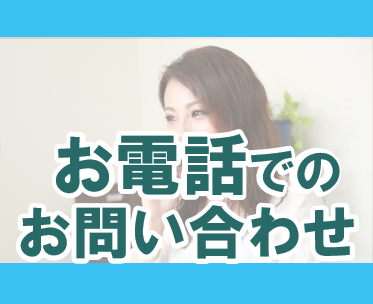 | 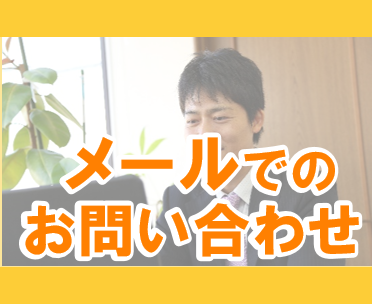 |  |
お電話いただくか(タップで電話が掛かります)、下記の「無料面談申込みフォーム」に、ご希望の日時を第3希望まで入力してご送信ください。
フォームを送信いただいた翌日以降に、ご希望の時間に予約をお取りできるかを弊社よりご連絡いたします。
または画面右下のチャットボットからお問い合わせください。
メール問い合わせはこちらから!
メールでお問い合わせされる方は、下記項目にご入力後、一番下の「この内容で送信する」ボタンをクリックしてください。
※ご入力のメールアドレスを今一度ご確認下さい。
宜しければ「この内容で送信する」ボタンをクリックして送信して下さい。
お気軽にお問い合わせください。
この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。

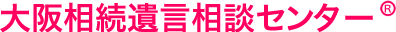
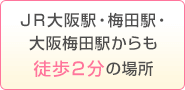
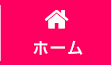
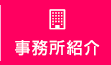

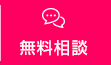


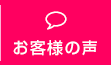


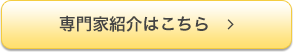
.png)
.png)
.png)